夏キノコ観察!アカヤマドリは山のデザートだった…?
梅雨も終わりに差し掛かり、季節はすっかり夏。
今年もそろそろ夏のキノコが出る時期ではないかと、近所の山に行ってきました。

と、いつものポイントまで歩いている途中でノウタケさんの幼菌がお出迎え。
コイツも毎年同じ場所に生えるんだけど、食べたことないんだよね。似たような見た目のオニフスベがクソまz…あまり口に合わなかったからか、なんとなく避けてる感がある。
まあ、機会があったらちょっと味見してみても良いかもね。

そして、そこから20分ほど歩き、目的のポイントに到着。
ここはかなりの山奥でほとんど人も見かけないのですが、藪の中にはブナ・マツなどが多数生育しており、適度な湿り気もあって、この時期には様々なキノコたちが生えてくれる穴場スポットです。
ちなみに皆さんご存じかと思いますが、一般的には杉・ヒノキなど低山でよく見られる人工林においては、ほぼ皆無と言って良いほど食用のキノコは発生しません(オオイチョウタケなどの例外もある)。
ですので、キノコ狩りをする際は、まずブナ科広葉樹。そして松が生えているかどうかをポイント探しの目安にすると良いでしょう。そのような混生林であり、更に北向きのジメジメした斜面であればまず間違いなく大量のキノコが見られるはずです。

テングタケ? 毒。
ポイントに進入して、まず目につくのは大量のテングタケ科キノコたち。

デカイ。
しかし、タマゴタケなどの代表的な食菌は見つからず、どんどん奥へ奥へと進みながら、写真を撮るだけの時間が過ぎていきます。いや、これはこれで楽しいんですが、せっかく来たんだから美味しい夏キノコの一つや二つは持って帰りたいところ。
てか、テングタケ生えてるのにタマゴ生えてないとかどういうことなの。
鹿とかもキノコ食うっていうし、もしかして美味いやつは根こそぎいかれてるのかな? まあ、単純に人が入ってる可能性もあるけど。

シロキクラゲ。綺麗だし食べられるけど…ちっちゃい!
その後、一時間ほど歩き続け、休憩のため一度山道に戻ることに。
落ち葉だらけの獣道を下りながら、『目が慣れているうえ、下りだと見渡しが良いためキノコは帰り道のほうが見つけやすい』という、どこで聞いたのかも分からないような情報を頼りに、地面をひたすら見る(滑落する恐れもあるので真似しないように)。
すると・・・

お、お前は・・・
アカヤマドリ様!
本種は夏キノコの代表格であるイグチ科のキノコで、なんとあの高級キノコ”ポルチーニ”にも近い仲間。当然、図鑑などにも『非常に美味である』という記載もあり、私にとっては思わず様づけしてしまうほど憧れのキノコでした。
ここでコイツに会えるとは…一本だけとはいえ来てよかった。
採取して見ると、中は締まっており、虫食いの被害も少ない様子。
このキノコは干して保存食にも出来るそうですが、せっかくの初採取なので、さっそく家に持って帰って食べてみましょう。
憧れのアカヤマドリを食す。

というわけで、自宅。
こうしてみるとなんかちょっと可愛いですねw

柄を割ってみると、ごくわずかな空洞はあるものの、肉はかなり残っており状態も良さそうです。
とはいえ幼菌が一本だけですし、問題はこれをどうやって調理して食べるかですが、今回はバターと砂糖で炒めて”バターシュガーソテー”にしようと思います。
キノコに砂糖!? と、思われるかもしれませんが、このアカヤマドリはもともと多少の甘味があり、砂糖と合わせることで美味しく頂けるそうですので、経験として一度やってみるのも良いかと。

いざ調理。
まあ、フライパンに軽くバターをしいて、砂糖とともにじっくり焼くだけですが。
焼いている内に、なぜかマツタケに近いような高級キノコ特有の香りがしてきました。ただ、ポルチーニっぽい香りはあまりありませんね。

完成!
食べてみると、確かに噛むにつれて砂糖以外の独特な甘味を感じますね。アカヤマドリには特有のニオイというか、あまり良い香りとは言えないような風味があると聞いていたのですが、これは他のイグチ科キノコと大差ないように思います。
あと、砂糖が付いている部分にちょっと焦げが出来ているのですが、ここが抜群に美味しいですね。カリっとした食感と香ばしさ、それに上品な甘みが合わさってまさにスイーツって感じがしますね。
まとめ
まあ正直言って思っていたほど感動的な味ではありませんでしたが、確かに美味しかったですね。これは見つけ次第、採取確定のキノコとして覚えておこう。
まとまった量が採れたらクリームパスタにでもして再評価したいと思います。
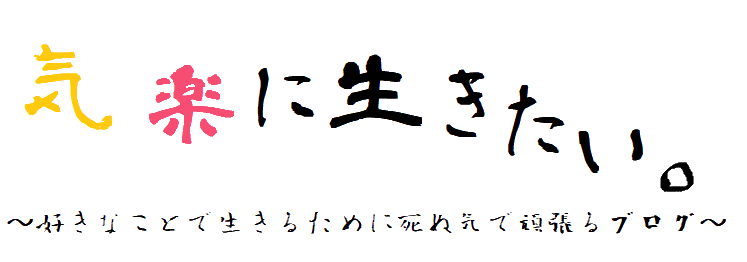

















ディスカッション
コメント一覧
ズキンタケはたべられますか
食毒不明ですし、なによりあのサイズのものをあえて食べるメリットがあるかを考えると、あまり確かめたいとも思えないです。
質問者様にパッションがあるなら挑戦し結果報告いただけると嬉しいです!
(※責任は負いかねます)